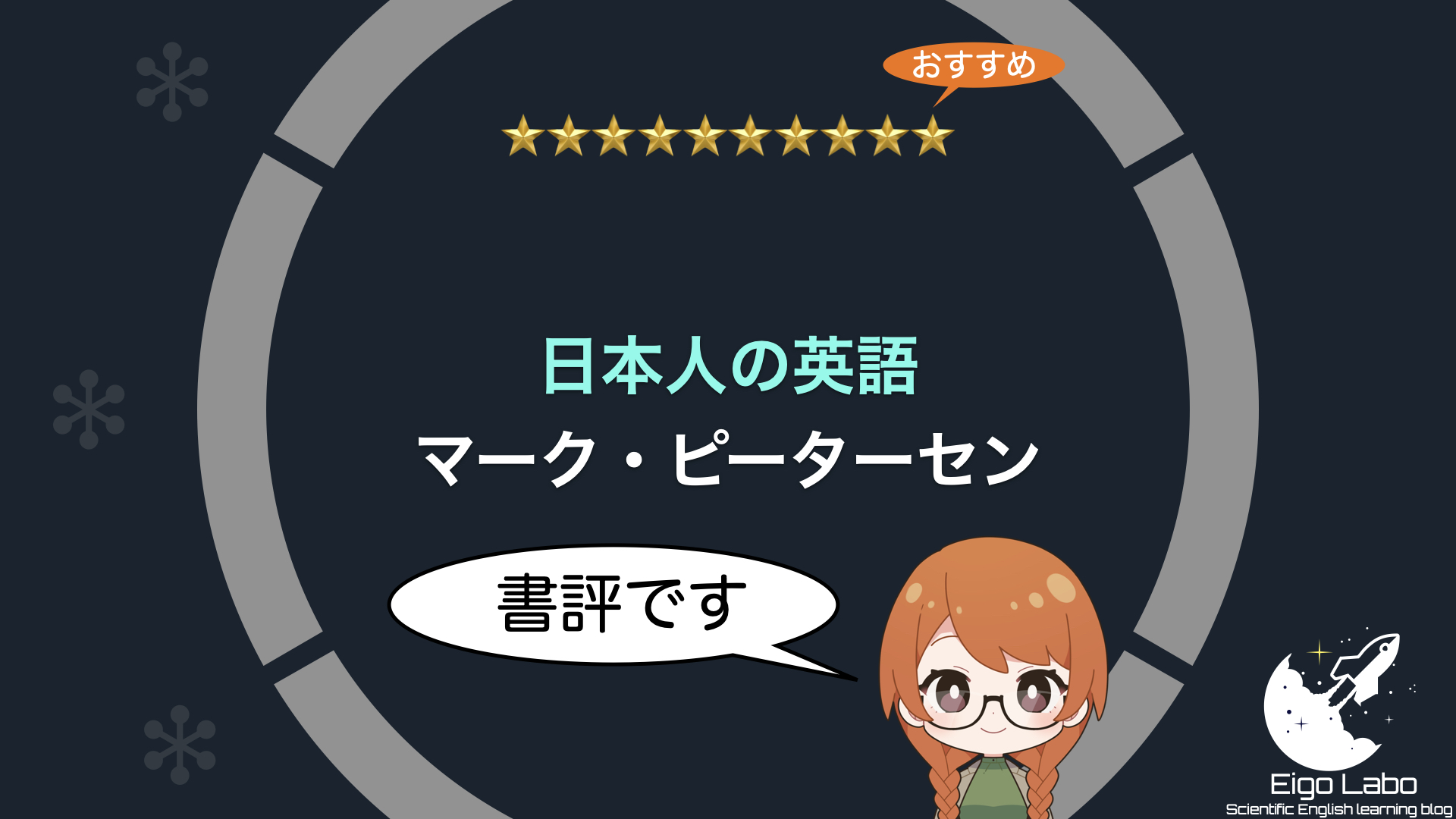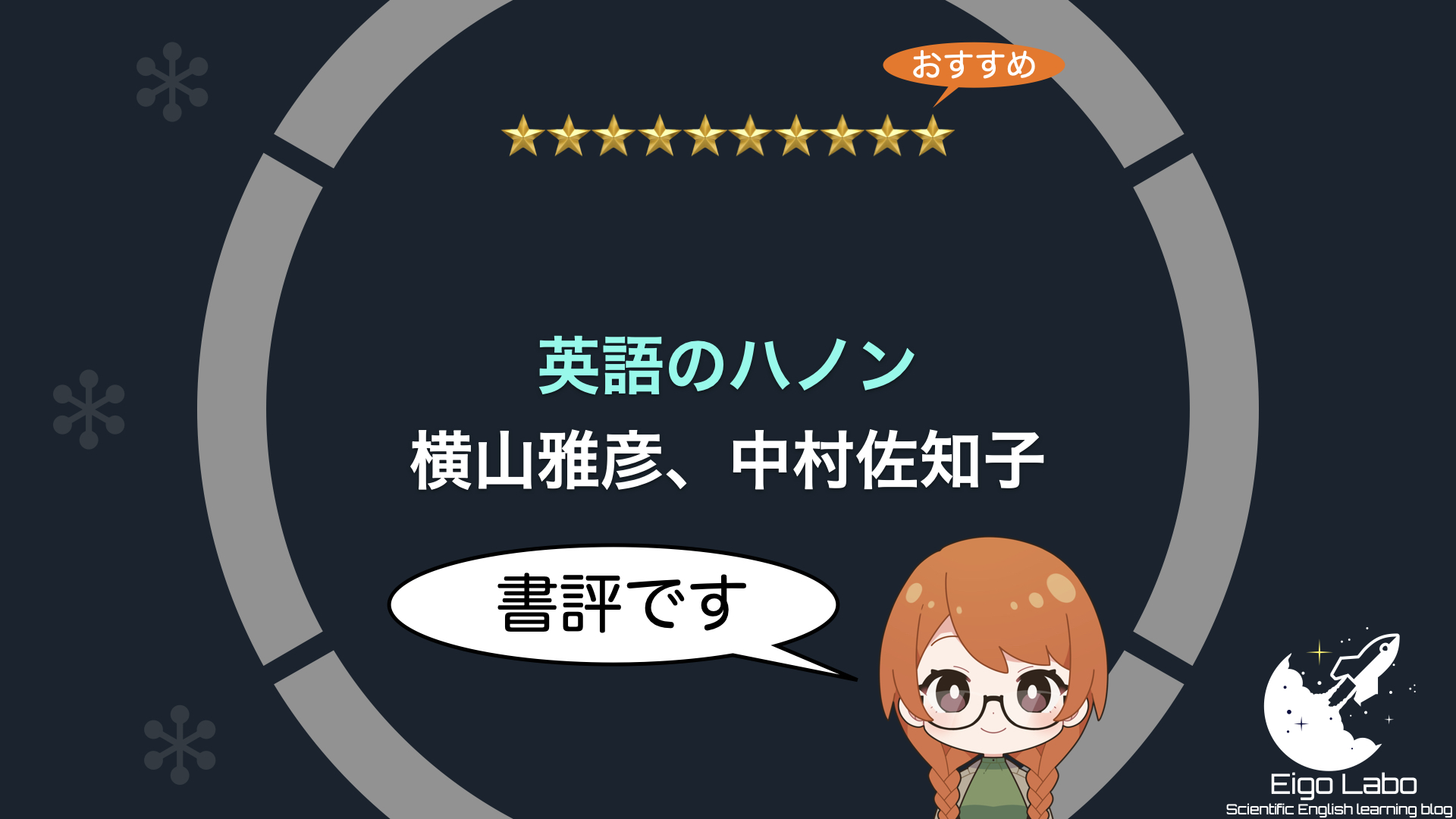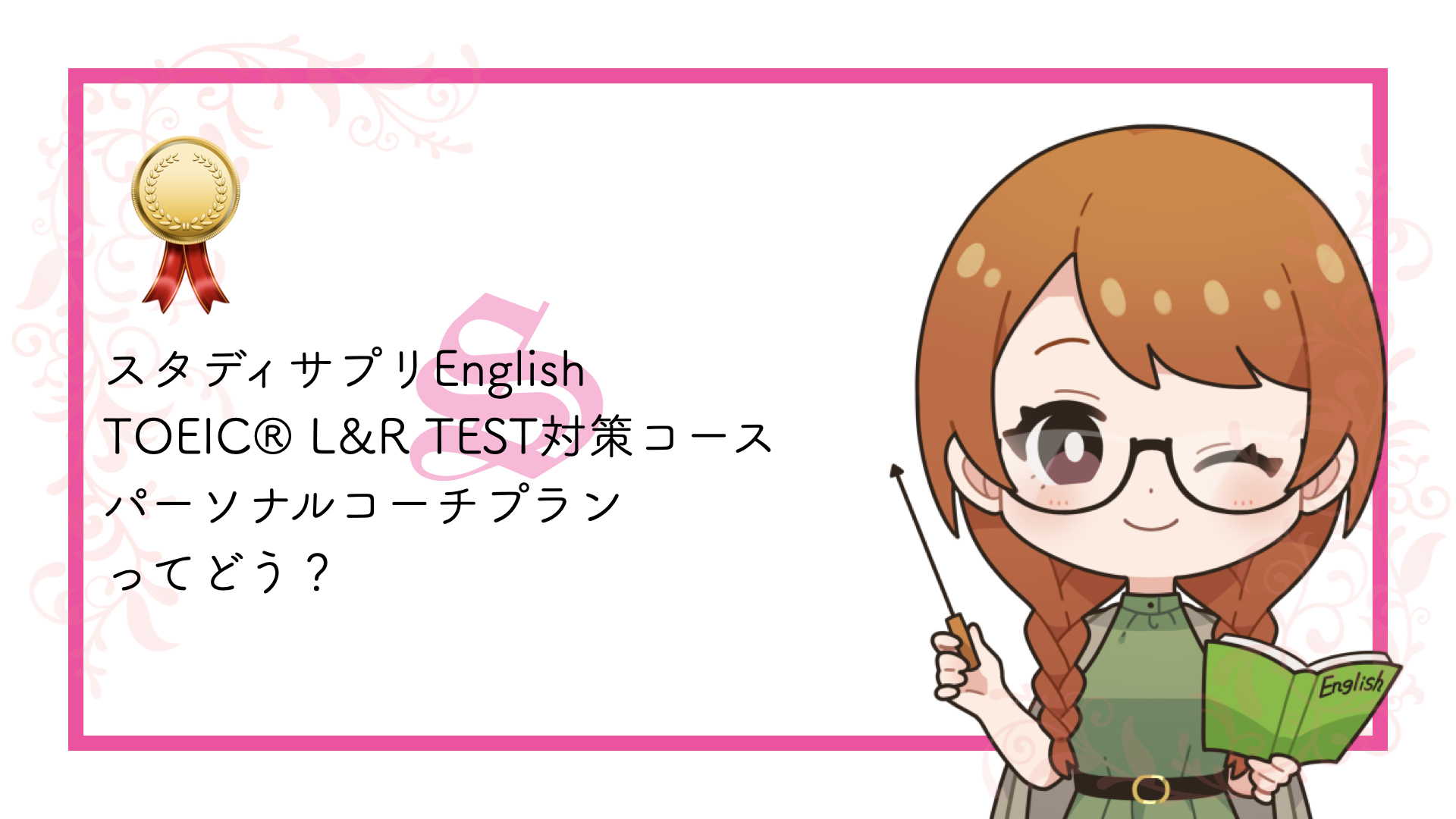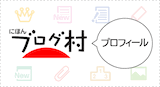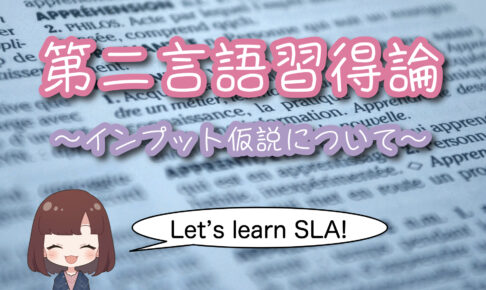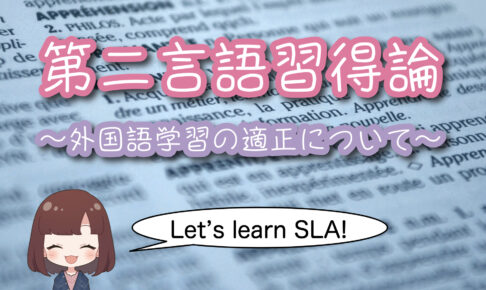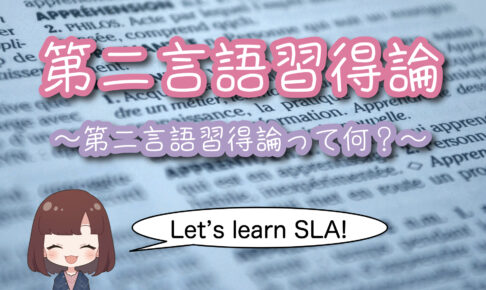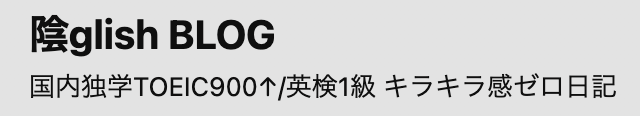このブログではおなじみの第二言語習得論ですが、今回も新しいお話をしたいと思います。

今回は何ですか?
今回はアウトプット仮説についてお話します。

うん、第二言語習得論という言語学の一分野で登場する説だからね。
難しく聞こえるかもしれないけど、第二言語習得論において英語学習におけるアウトプットがどう見られているか今回理解できると思うわ。
エイコちゃんも気になるでしょ?アウトプットが英語学習にどれだけ大事か。

うん、エイコちゃんのように興味がある人には今回の記事はマッチすると思うわ。
さて、このブログでは第二言語習得論を扱っています。
他の記事が気になる方は下記リンクからどうぞ。
他の記事はこちら!↓
それでは「スウェインのアウトプット仮説って何?優しく解説します!」と題して始めます。
今回の記事は次の書籍を参考にしています。
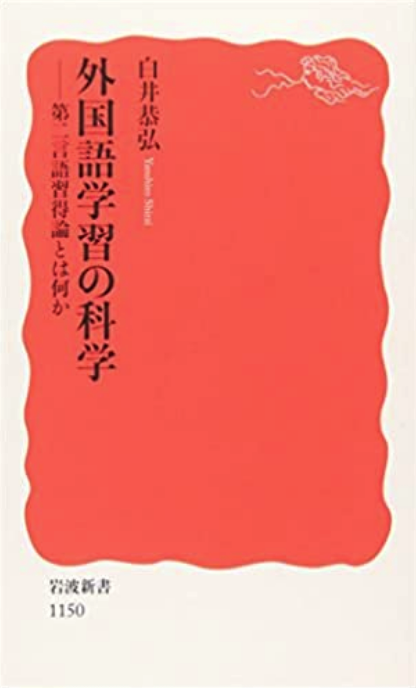
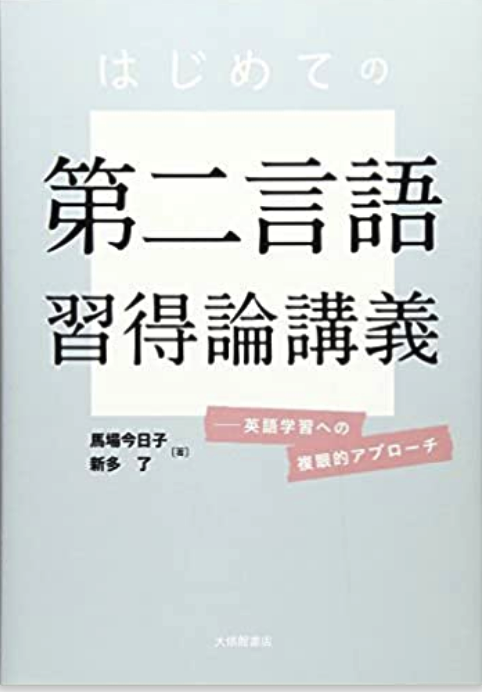
スウェインのアウトプット仮説とは?

まず、言語習得の世界ではインプット(聞く・読む)だけで言語習得が可能なのか、アウトプット(話す・書く)が必要かって論争があるの。
結論として、インプットが言語習得の必要条件であるということに関して、第二言語習得の研究者の間で意見の一致が見られたってことになるわ。
だけどね英語「で」教育を受けた(イマージョン教育と言う)子どもたちが聞き取り能力はネイティブと差はないのに文法的な正確さ、社会的に適切な表現(話す相手による表現使い分け)においては劣っているという調査結果が出てきたの。
この調査をしたのがトロント大学名誉教授のメリル・スウェインなの。

彼女はアウトプットすることにより正確な英語が身に付くと主張しているわ。
※アウトプットのみで言語習得できるという意味ではないので注意。

いい質問ね、エイコちゃん。
それについて話すわね。
アウトプットの効用1:自分の気付き

えっと、エイコちゃんは英会話ってしたことがあるかしら?

なるほどー。
そこで聞きたいんだけど、実際に英会話してみて
- 自分はこれは言えたなー
- 自分はこれは言えなかったなー
って気づきはあったかしら?

「心地よい天気」をcomfortable weatherって言えなかったなーって気づいたときがありました。
comfortableって私の中では当たり前過ぎて使いこなせるだろうって思っていたんですけど、
いざ英会話してみると、言えなかったんです。
そうね、それが自分の気づき。
自分ができると思っていること、実際の能力。
このギャップに気づくきっかけとなるのがアウトプットね。
ただ、リハーサルでも同様の効果が得られることは言っておくわ。
アウトプットの効用2:仮説検証

仮説検証ができるのはアウトプットの効用として挙げてもいいわね。

「あの英語表現って通じるかなー・・・?」っていうのを検証してみるっていうのが一例ね。
これは私の例なんだけど、「『しかし』のbutを意図的にhoweverって言い換えたら、相手に硬いって言われるかな?」
「『考える』のthink aboutを意図的にconsiderって言い換えたら、相手に硬いって言われるかな?」
…というのを検証したことがあるわ。
ちなみに私の経験では指摘されなかったわ。

アウトプットの効用3:自動化


うん、自動化。
英会話を例にすると、発話をするまでに次のプロセスが考えられるわよね。
- 相手の音声を知覚し
- 相手の発話内容の意味理解をし
- それを踏まえて自分の返答内容を概念化
- 文法に従い文を作り
- それを音声にする
これらのことを自動でできるようにするためには話す練習が効果的と考えられるわよね。

語学学習ではインプットが重視されているけど、発話に関してはアウトプットがないと厳しいと私は思うわ。
スウェインのアウトプット仮説で注意すること


別の記事でクラッシェンのインプット仮説について触れたんだけど。
その内容は「インプットのみで言語習得が可能」というものだった。
この記事です!
それで注意したいのは、
スウェインのアウトプット仮説は「アウトプットのみで言語習得できる」っていう説ではないことね。
あくまで学習の基本はインプット。
その上でアウトプットが必要というのがスウェインのアウトプット仮説。
そこは認識しておきましょうね。
アウトプット仮説を踏まえてどう英語学習に活かすか?


「インプットを中心的に行い、アウトプットで効率を上げる」になるかしらね。
まず、第二言語習得論ではインプットの重要性は多くの研究者に支持されている。
だから英語学習においてインプットは基本になる。
だけどインプットだけでは効率はよくない。
例えば、英単語を覚えるというインプットがあったとしても、テスト等の「アウトプットの必要性」がないと定着が難しいでしょう?
ただ十分なアウトプット無しにアウトプットばかりに重点を置いても言語習得は進まない。
なぜならアウトプットって自分の既知の知識を使って何かをすることに過ぎないから、新しく知識が増えるわけではない。
ということで繰り返しになるけど「インプットを中心的に行い、アウトプットで効率を上げる」になるわね。

まとめ

今回のお話で分かったわね。
英語学習においてインプットは大事だけどアウトプットを抜かすと効率が落ちる。
インプットばかりの勉強をする人にはこのことを教えてあげるといいわね。

さて読者のみなさんの英語学習はインプット、アウトプット、バランス良く取れているでしょうか?
インプット、アウトプットの適切な配分は人それぞれでしょうが、もし結果に伸び悩んでいたら配分に問題がないか見直してみるのもありかもしれませんね。
それでは、引き続き勉強を頑張っていきましょう。

メール相談受付中
ブログに対するご意見、
英語の勉強法についての相談、
気軽にしていただけたらと思います。
管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪
(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)